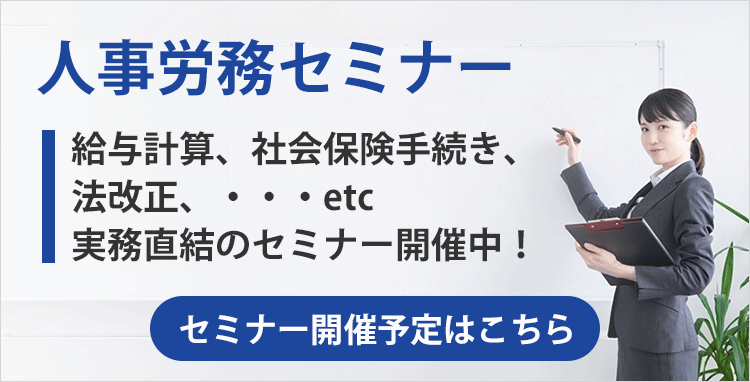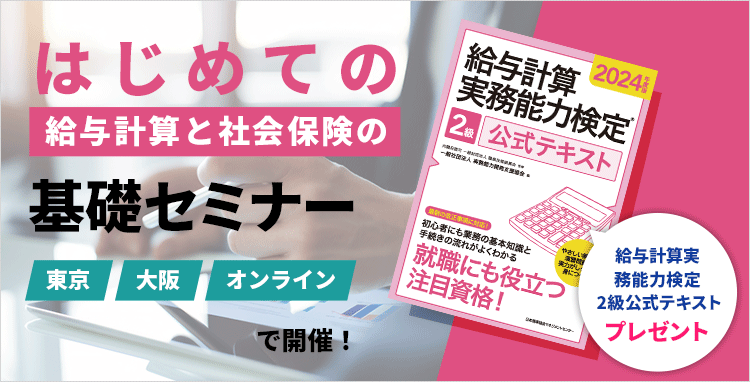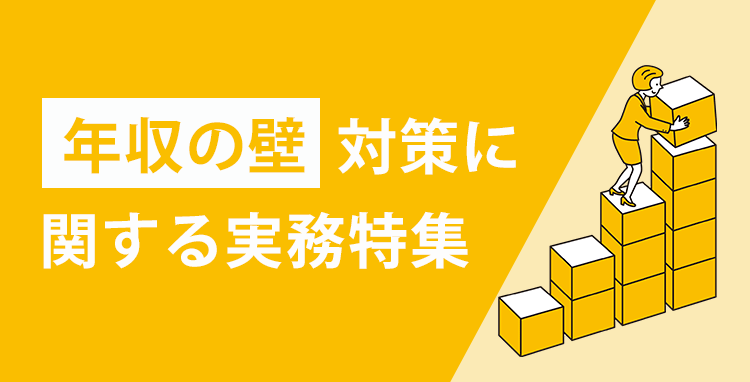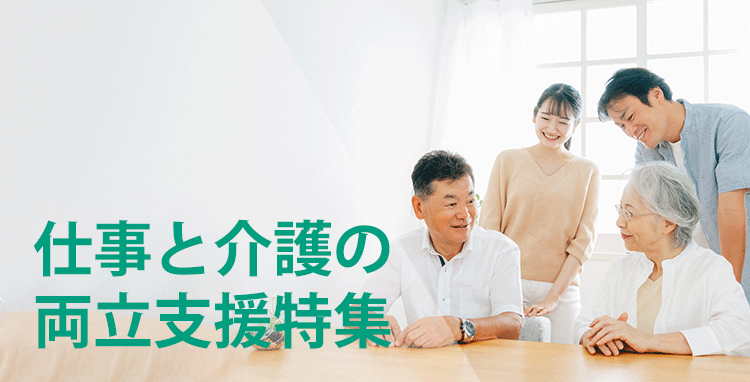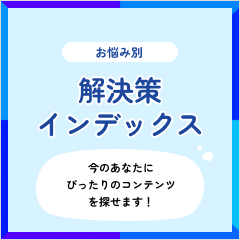3つの固定観念にとらわれない。「子育てにやさしい会社」を目指すポイント
<ごとう人事労務事務所 後藤和之/PSR会員>
国が、こどもに関する施策を強化している中で、経営戦略として「子育てにやさしい会社」を目指したい場合に、どのような点に留意すれば良いのでしょうか。
今回は、令和5年4月に施行された「こども基本法」の条文を手掛かりに、とらわれやすい‘’3つの固定観念‘’を取り上げ解説します。
~避けるべき固定観念①~こどもの年齢
まず、こども施策に関わる大きな流れとしては、令和5年4月に「こども家庭庁」が設置されたこと、「こども基本法」が施行されたことです。
「こども基本法」の第2条1項では『こども』について、次のような定義があります。
(定義) 第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
|
ポイントは、「18歳まで」「20歳まで」などの年齢を定めていないということです。
こども家庭庁の資料では、次のように説明しています。
Q「こども」とは、何歳までのことですか? A こども基本法では、18歳や20歳といった年齢で必要なサポートがとぎれないよう、心と身体の発達の過程にある人を「こども」としています。こどもや若者のみなさんのそれぞれの状況に応じて、社会で幸せに暮らしていけるよう、支えていきます。
|
年齢を定めることで「必要なサポートがとぎれる」弊害も考えられるということです。
もちろん、年齢を定めているからこそ、こどもの発達に応じた重点的な支援を行うこともできます。
しかし、支援対象の要因となるすべてのことが、こどもの年齢に起因しているものではなく、こどもの発達過程も一人ひとり違います。
それは「18歳」「20歳」だけでなく、「1歳」「3歳」「就学前」「義務教育終了」なども同じことがいえます。
こどもの年齢に応じた、発達過程の大まかなイメージというものはありますが、それが固定観念になってしまうと、こどもの発達過程によっては必要なサポートがとぎれる原因にもなりかねません。
一方で、それぞれの施策・法律には年齢の定めは必要であり、だからこそ、こどもに関する施策の基本となる「こども基本法」を制定することで、その弊害を少なくする社会をつくる必要があるのです。
~避けるべき固定観念②~自らの価値観
自らの立場や経験に基づいた「価値観」。その「価値観」によって、子育てに対してのイメージもだいぶ変わっていきます。
ここでは、その価値観が固定観念となり、「子育てにやさしい会社」への弊害となっている例を紹介します。
(例1)子育て経験がない「役員Aさん」
|
Aさん「従業員が育児休業を取ってしまうと、他の従業員の仕事の負担が大きくなってしまう。だから、こどもが1歳になるまで休みを取ったら、その後はフル回転で働いてください」 |
このようなAさんの価値観は「育児休業の対象とならない従業員への配慮」「育児休業後への叱咤激励」などの思いがあるのかもしれませんが、間接的に「育児休業を取得するな」という解釈にもなりかねません。
さらには、1歳になったからといって子育てが終了するわけではありませんので、子育てをする従業員への配慮に欠けてしまう印象へとつながってしまいます。
(例2)子育て経験がある「上司Bさん」
|
Bさん「私が子育てしていたころは、こんなに育児の制度は充実していなかった。最近の若い人たちは‘’子育てが大変だ‘’とすぐに泣きごとを言ってくる」 |
このようなBさんの価値観は「制度に頼らなくても、仕事と育児は両立できるはず」という強い自負があるのかもしれません。
もちろん、子育ての先輩としてBさんの姿勢から学ぶべきこともたくさんあると思います。
しかし、時代の変化とともに、「社会」「地域」「子育て」を取り巻く環境、そして何より「こども」を取り巻く環境が変わってきています。
過去の経験から導かれた自らの価値観より、現在の「こどもたちにとって、必要な環境は何なのか」を考える視点が「子育てにやさしい会社」を目指すには大切なことです。
(例3)子育て中の「同僚Cさん」
|
Cさん「●●さんと同じ学年の小学生の子育てをしているが、なぜ●●さんは、よく休みを取るのか」 |
このようなCさんの価値観は「育児休業などの制度を必要とする時期は、誰もがある程度は同じであるはず」という認識があるのかもしれません。
実際に制度の多くは、こどもの年齢に制限があります。
しかし家庭の事情はそれぞれで、例えば小学校1年生のこどもが発熱したときに、配偶者や親戚がいれば看病をしてもらうことができますが、看病する人がいなければ会社を休まざるを得ません。
そのような事情は周りが知らないことも多いので、Cさんもそのような不満を抱くのかもしれません。
しかし、自らの価値観は一旦隅に置いて‘’家庭環境はそれぞれ‘’という認識を持つことが大切です。
~避けるべき固定観念③~法律の最低基準
まず前提として、育児・介護休業法にある年齢・期間・時間数など「最低基準」を遵守することが前提です。
ただし今回は「子育てにやさしい会社」を目指すことがテーマですので、一歩踏み込んで「最低基準に縛られないこと」をポイントとして解説します。
先ほどの例で、役員Aさんが「こどもが1歳になるまで休みを取ったら、その後はフル回転で働いてください」という形で「1歳」という年齢が出てきたのは、おそらく「育児休業が原則1歳まで」という認識があるからだと考えられます(保育園に入れないなどの事情がある場合は除く)。
「1歳」というのはあくまでも『育児休業』に関しての基準です。
その「1歳」に固執をしてしまうと『短時間勤務制度(3歳未満)』『時間外労働の制限(小学校就学前)』などの制度があることを見落としがちになります。
また、会社の方針として『育児休業』の年齢上限を上げて、例えば3歳にしても良いわけです(ただし、雇用保険の育児休業給付金の対象とはなりません)。
さらに視点を変えれば、必ずしも、こどもが1歳になるまで休む必要もありません。
1歳になる前から適度に仕事をした方が、子育てにも良い影響が生まれるのであれば、そのような選択肢でももちろん良いのです。
大事なことは「法律の最低基準」という固定観念に縛られずに、その人にとっての「最適なワークライフバランス」を実現することです。
一人ひとりのワークライフバランスの実現が「子育てにやさしい会社」へ近づいていくことになります。
プロフィール
昭和51年生まれ。日本社会事業大学専門職大学院福祉マネジメント研究科卒業。約20年にわたり社会福祉に関わる相談援助などの業務に携わるとともに、福祉専門職への研修・組織内OFF-JTの研修企画などを通じた人材育成業務を数多く経験してきた。特定社会保険労務士として、人事労務に関する中小企業へのコンサルタントだけでなく、研修講師・執筆など幅広い活動を通じて、“誰もが働きやすい職場環境”を広げるための事業を展開している。
このコラムをお読みの方にオススメの「仕事と育児の両立支援」コンテンツ
特集:産休・育休・職場復帰の実務
 >>>特集はこちら
>>>特集はこちら
【オンデマンド配信】2025年4月以降 育児介護休業法・雇用保険法・次世代法の法改正対応の実務 解説セミナー
 >>>詳細・お申し込みはこちら
>>>詳細・お申し込みはこちら