2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されるなど、社会全体で育休取得を推進する動きが進んでいます。
一方で、初めて育休を取得する従業員にとっては、未知の経験により悩みを抱え込むこともあるかもしれません。今回は、会社が従業員の「初めての育休取得」へ配慮するポイントを解説します。
育休へのフォロー①育休中の会社・職場の様子を伝え「不安感へのフォロー」を
産後パパ育休などの短期間の休みも考えられますが、数か月から1年にわたって会社を休むという経験自体が初めての従業員も多いと思います。
そして、従業員は育休中にさまざまな不安感を感じることが多いかもしれません。
例えば「他の従業員へ引き継いだ仕事はどうなっているのだろうか」「育休終了後に、スムーズに職場へ復帰できるだろうか」などの不安です。
そのような不安を解消するため、ぜひ会社・職場の様子を要所要所で伝えていきましょう。
例えば、次のようなことです。
・社内報を送るとともに、メールなどで職場の様子などを一言添えておく
・従業員が担当していた仕事に成果が出た時に、感謝の言葉を伝える
・社内専用のポータルサイトなどにより、定期的に会社の情報を伝える など
その時に注意すべきことは「過度なフォローになりすぎないこと」です。
あまりにフォローが強いと、従業員にとって過度なプレッシャーになることも考えられますので、会社・職場の実情に合った適度なフォローを意識しましょう。
育休へのフォロー➁育休取得者へ寄り添い「育児・家庭へのフォロー」を
育休中の家庭内の役割は、それぞれの家庭の状況によって様々です。
例えば、夫婦間で「育児」「家事」などを最初から分担する家庭もあれば、「互いに気づいたことをする」といったように、明確に分担しない家庭もあるでしょう。
近隣に祖父母などがいれば、育児を手伝ってもらうこともあるかもしれませんし、祖父母などがいなければ、地域の子育てサービスを積極的に利用するかもしれません。
どのような役割を担うことが良いのかは家庭それぞれです。
しかし、少なくとも初めて育児休業を取得する場合には、事前に経験がありませんので、最善の方法を模索することになり、一人で悩みを抱え込んでしまうこともあるかもしれません。
会社としては、ぜひ育休取得者に寄り添い、育児・家庭へフォローする姿勢を示していきましょう。
例えば、次のようなことです。
・会社に相談窓口を設置し、育休中の悩みを聞くことができるようにする
・労務担当や職業家庭両立推進者などが、育休中の様子などを聞いてみる
・育児中または育児経験者の自主グループをつくる(ママ会・パパ会など)
先ほどの「不安感へのフォロー」と同じことですが、こちらも注意すべきは「過度に踏み込みすぎないこと」です。
育児や家事は、あくまでプライベートなことですのでさりげない配慮を示す程度に意識しましょう。
育休へのフォロー③家庭の実情に応じ「制度選択へのフォロー」を
育休中にざまざまな経験をすることで、当初予定していたことと変わることがあるかもしれません。
また、育休終了後にも、時間外労働の制限・短時間勤務制度などの制度を活用することも考えられます。
従業員が、主体的に育児休業に関する制度が選択できるようフォローしていきましょう。
例えば、次のようなことです。
・育休期間中に、育休期間(育休終了時期)について従業員とあらためて確認してみる
・育休終了後に、あらためて育児に関する制度(時間外労働の制限など)を伝える機会をつくる
・テレワークやフレックスタイム制など、新たな働き方を従業員とともに考えてみる など
会社で掲げている‘’育休取得の方針‘’を踏まえつつ、ぜひ従業員の「制度選択を尊重」し、それぞれの家庭の実情に応じた選択のフォローを意識していきましょう。
プロフィール
昭和51年生まれ。日本社会事業大学専門職大学院福祉マネジメント研究科卒業。約20年にわたり社会福祉に関わる相談援助などの業務に携わるとともに、福祉専門職への研修・組織内OFF-JTの研修企画などを通じた人材育成業務を数多く経験してきた。特定社会保険労務士として、人事労務に関する中小企業へのコンサルタントだけでなく、研修講師・執筆など幅広い活動を通じて、“誰もが働きやすい職場環境”を広げるための事業を展開している。
このコラムをお読みの方にオススメの「育児両立支援」コンテンツ
2025年義務化対応 育児従業員説明用セット~妊娠・出産等申出時/3歳になる前~
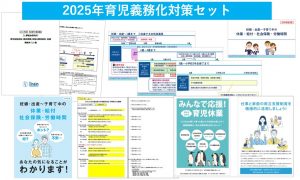 改正育児介護休業法で企業に求められる措置のうち、「個別周知・意向確認」「個別の意向聴取」の実務対応に特化した義務化支援セットです。
改正育児介護休業法で企業に求められる措置のうち、「個別周知・意向確認」「個別の意向聴取」の実務対応に特化した義務化支援セットです。
人事担当者向け「実務ポイント集」、従業員向け制度説明用動画、義務化対応した従業員説明用冊子、個別面談等の際の案内資料作成支援ツールなど必要なツールを一式揃え、会社のスムーズな義務化対応を徹底サポート!
2025年10月の施行に備え、今からの準備にぜひご活用ください。
>>>詳細・ご購入はこちら
【キャンペーンセット販売】育児従業員説明用セット+出産・育児制度<個別案内>Excelツール 7月31日まで
個別周知を手厚く実施したい企業様へ。上記育児従業員用セットと、育休の取得可能期間、社会保険料免除等の期間、給付金の概算額など、より詳しい案内資料が作成できる実務支援ツールとのセットを7月末まで限定で販売しております。
















