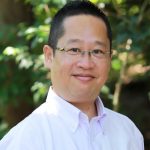2025年1月、労働基準関係法政研究会により今後の労働基準関係の法律について検討が行われ報告書が公表されました。
労働基準法は昭和22年に施行された法律ですが、これまで時代に合わせて改正が行われてきましたが、テレワークやフリーランスの普及により更に見直しが行われようとしています。
まだ具体的な法改正には至っていませんが、今後どのように変化していくのか注視していく必要があります。
今回提出された報告書から企業が対策をしておくべきことを見てみましょう。
「労働者」と「事業」の定義について
まず、労働基準法において、「労働者」とは『職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者』と定めています。
「使用される者」とは、会社側から指揮命令を受ける者ということになるのですが、たとえば契約上はフリーランスとして請負契約をかわしていたとしても、実態として労基法上の労働者に該当するのかどうか個別に判断されることになっています。
ただ、フリーランス法が昨年11月に施行された関係上、労働者性の適正な判断を求める声が大きくなってきています。
企業側の対策としては、雇用契約・請負契約を結ぼうとするときに、契約書で雇用契約なのか請負契約なのかを明記し、それぞれの働き方に応じた業務の進め方をお互いに確認をすることがトラブルの防止につながります。
次に「事業」についての考え方ですが、労働基準法においては、『場所』を単位として適用する形式を採用しています。
つまり、事業を企業全体として見るのではなく、本社、営業所、工場などそれぞれの場所に存在している空間を事業場として認識します。
したがって、就業規則や36協定などの作成について事業場ごととしているのもそのためです。
ですが、新型コロナウイルスの感染拡大を機にリモートワークが急速に普及し、出社をせず自宅等で仕事を行うスタイルが定着しました。
では、業務を行っている自宅が「事業場」として認識されるのかというと、そうではなく通達では、「規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う」としています。
つまり、在宅勤務をしていても、その従業員が所属している営業所などの組織を労働者が属する事業場となります。
とはいうものの、事業場単位での適用となる就業規則や36協定、変形労働時間制にかかる労使協定などを現実に運用するには複雑なものとなる可能性があります。
しかも、営業所等の事業場では労務管理が行われておらず、本社で一括して管理されているケースも目立っています。
そうなると、就業規則の作成・変更や36協定の締結などについて、条件を満たせば本社で一括して届け出ることができるものの、事業場単位での届出であることには変わりありませんので、今後の手続き簡素化が望まれるところです。
逆に、行政側から見た場合、たとえば労働基準監督による指導・監督については、事業場単位ではなく、企業単位で行うようになるかもしれません。
したがって、本社などの管理部門と、支店や労働者の「自宅」など現場サイドとの、より密なコミュニケーションが求められるようになることは間違いありません。
そのために、就業規則の整備などの対策はこれから準備しておきたいところです。
労働時間に対する考え方はもっと厳しくなる?
労働基準法では、労働時間は原則として、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間までと規定されています。
これが、時代の流れにともなって、変形労働時間制やフレックスタイム制が整備され現状の働き方に合うよう法改正が重ねられ、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度が導入されるに至りました。
しかしながら、従業員の健康を守る意識も高まっており、長時間労働への規制も厳しくなっています。
たとえば36協定における時間外・休日労働の上限規制が適用されていますが、今後は連続労働日数や休日労働の回数について、目が向けられるようになります。
たとえば、休日について、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば法違反にはなりませんので、4日の休日を固めて与えれば、残りの日数についてはすべて労働日とすることが理論上可能となります。
ですが、従業員の心身の健康を守るために、今後連続する労働日数について制限を設けられることになるかもしれません。
なので、いまから職場環境の見直しを行い、従業員が適正に休日を確保できるようにしておくことが求められます。
いかがでしょう、今後ますます働き方に関する基準が上がっていくことになり、企業の経営とのバランスを取らなければならなくなります。
法改正が行われる前に、出来る対策を今から行うことをお勧めします。
プロフィール
ひろたの杜 労務オフィス 代表(https://yoshismile.com/)
営業や購買、総務などの業務を会社員として経験したのち、社会保険労務士の資格を取る。いくつかの社会保険労務士事務所に勤務したのち独立開業する。現在は、労働者や事業主からの労働相談を受けつつ、社労士試験の受験生の支援をしている。