子どもが生まれた直後は、育児はもちろんですが、それ以外にも役所への様々な手続きなどしなければならないことがあります。
そこで、産後8週間の期間に活用できる出生時育児休業、そして、その間に受け取れる給付金として今回ご紹介する出生時育児休業給付金があります。
本コラムでは、出生時育児休業給付金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。
記事一覧はこちら>>>人事担当者のための社会保険とお金の知識
出生時育児休業給付金とは
前回のコラムでご紹介したのは育児休業給付金でしたが、今回は出生時育児休業給付金についてです。
育児休業給付金と大きく異なるのは、支給されるのは出生時育児休業、通称「産後パパ育休」と呼ばれる休業を取得した方が対象で、主に男性が受け取れる給付金という点です。
女性の場合は?ということを先に申し上げますと、出産予定日以前6週間から出産後8週間は原則として労働基準法で仕事を制限されている産前産後休業期間とですので、この期間に仕事をお休みしたのであれば、その期間の所得補償として健康保険から出産手当金が支給されます。
また、産前産後期間終了後に育児休業を取得する場合は、その期間、一定の条件を満たしていれば、前回のコラムでご紹介した育児休業給付金が、雇用保険から支給されます。
一方、男性の場合、あるいは産後休業を取得しない女性の場合も対象となりますが、子どもが生まれた後は、もちろん育児休業を取得することができて、条件を満たせば、同じように前回コラムでご紹介した育児休業給付金を受け取れるのですが、原則として育児休業期間中は仕事ができず、また、以前は育児休業を分割して取得することも認められていませんでした。
これが2022年の10月から、出生時育児休業、通称「産後パパ育休」という制度が始まり、妻の産後休業の期間、すなわち産後8週間の期間であれば、最大28日間、2回に分けて休業することが可能になり、しかも、休業期間中も一定の範囲内(詳細は後述)であれば仕事をすることができるようになりました。その上で、一定の条件を満たせば、この休業期間の所得補償として、雇用保険から出生時育児休業給付金が受け取れます。
実際に、お子さんが誕生してからやるべきことは、育児ももちろんそうですが、それ以外にも役所に出生届として子どもの名前を届けたり、児童手当の申請をしたり、公的な健康保険に加入したりする必要がありますし、出産した妻や生まれたお子さんが病院等から退院するときの付き添い等も大切です。
ですので、まとまった期間、仕事を休んで育児をするということが難しい場合でも、お子さんが生まれた直後の少しの期間、育児やその関連のことに充てられるということで、この出生時育児休業(産後パパ育休)が設けられたのです。
出生時育児休業給付金の金額
記事一覧はこちら>>>人事担当者のための社会保険とお金の知識
執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。
このコラムをお読みの方にオススメの「出産・育児支援」法対応関連コンテンツ
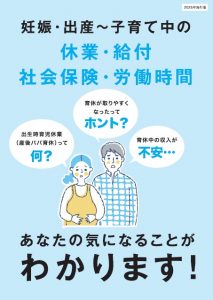 「妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間」従業員説明用冊子
「妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間」従業員説明用冊子
【社会保険労務士が執筆・監修】育児介護休業法で企業に求められている個別周知・意向確認用の従業員説明冊子です。2025年10月施行版の内容を盛り込んだ最新版です。ぜひ活用ください。>>>詳細・ご購入はこちら
【特別プラン】育児従業員説明用セット+出産・育児制度<個別案内>Excelツール
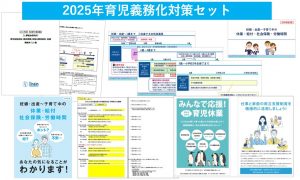 2025年10月施行 改正育児介護休業法を含めた個別周知・意向確認、個別の意向聴取の義務化対応に!「2025年義務化対応 育児従業員説明用セット~妊娠・出産等申出時/3歳になる前~」
2025年10月施行 改正育児介護休業法を含めた個別周知・意向確認、個別の意向聴取の義務化対応に!「2025年義務化対応 育児従業員説明用セット~妊娠・出産等申出時/3歳になる前~」
個別案内の実務を支援するExcelツール「2025年施行版 出産・育児制度<個別案内>Excelツール」のセット販売です。
















