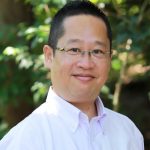近年、メンタルヘルス不調による休職者が増加していますが、従業員が復職するタイミングで労使トラブルが発生しやすく、企業側が復職を認めない場合、労使の紛争が長期化することもあります。
特に、企業が十分な根拠なく休職期間満了を理由に自然退職とした場合、法的なリスクが高まるのです。
厚生労働省が実施した令和4年の「労働安全衛生調査」によると、メンタルヘルス不調により1カ月以上の連続休業や退職をした労働者がいる事業所の割合は13.3%に上るとの結果が出ていますが、このような状況の中で、企業が求職者に対して適切に対応するためのポイントを解説します。
復職を認めなかったことで起こるトラブル
企業が従業員の復職を認めず、休職期間満了による自然退職とした場合、従業員が納得せず地位確認を求めて訴訟を起こす可能性があります。
もし裁判所が自然退職を無効とし、復職を認める判決を下した場合、判決が確定するまでの期間について未払い賃金を支払わなければならず、場合によっては数百万〜1000万円以上の支払になることもあります。
これは、裁判の判決に至るまでに1〜2年を要することが一般的であり、長期化するためで、企業に大きな負担を与えます。
さらに、企業の社会的評価にも影響を及ぼす可能性があるため、適切な対応が求められるのです。
それを踏まえ、従業員を休職させるときに気をつけなければならないことについてお話しましょう。
従業員を休職させる際に留意すべきこと
従業員が休職を希望する場合や、会社側が休職命令を出す前に、まずは医師の診断書を提出してもらい、症状や治療の進捗状況を正確に把握することが重要です。
加えて、可能であれば診断書を発行した医師との面談を行うための同意書を取得し、会社側が医師に直接治療方針について確認できる環境を整えておくことが望ましいでしょう。
次に、自社の就業規則を確認し、休職に関する規定を明確にしておく必要があります。
たとえば、「2週間以上連続して出勤できない場合」や「過去3カ月間で通算15日以上の欠勤があり、療養が必要と判断される場合」など、具体的な休職命令の条件を確認し、企業が適切に対応できるよう準備を整えます。
また、従業員の在籍期間によって休職期間が異なるケースもあるため、その点も把握しておくことが重要です。
復職プロセスの適切な管理
企業は、復職の可否を判断する際、就業規則を基に慎重に対応する必要があります。
まず、従業員の主治医が発行した「復職可能」の診断書のみで判断するのか、それとも会社が指定する医師の診察を必要とするのかを確認することが考えられます。
場合によっては、産業医との面談を経て最終的な判断を下すケースもあります。
また、休職開始時に主治医との面談の同意書を得ていた場合は、休職している従業員が従事していた業務内容や職場環境の情報を提供し、主治医から復職に関する意見を得ることが有効です。
企業が独自に判断するのではなく、医師の意見をもとに適切な対応を検討することで、トラブルのリスクを軽減できます。
もし主治医の診断書に「条件付き復職可」と記載されていた場合、その条件に応じた柔軟な対応が可能か検討します。
例えば、「短時間勤務なら復職可能」とされた場合には、リハビリ出勤の導入を検討し、初めは通勤のみを行い、次に数時間の勤務から徐々に勤務時間を延ばすなどの方法を取り入れることが考えられます。
ただし、残業が常態化している部署への復職は、安全配慮義務の観点から慎重に判断しなければなりません。
労働基準法第32条では、法定労働時間を超える労働は禁止されており、時間外労働はあくまで36協定に基づく免罰的措置に過ぎません。
そのため、企業は従業員の健康を最優先に考えた対応を行うことが求められます。
また、「原職復帰は難しいが、配置転換を行えば復職可能」とされた場合には、企業の規模や業務内容を踏まえた上で、従業員の回復状態に適した業務を割り当てることも一つの選択肢となります。
ただし、配置転換が難しい環境である場合には、復職が困難であるとして休職期間の延長を従業員と話し合うことが望ましいでしょう。
復職を認めることが難しい場合の対応
企業が従業員の復職を認められない場合、休職期間満了による自然退職とするのは紛争のリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
万が一、紛争に発展した場合には、労働局の助言・あっせん制度や裁判所の労働審判、さらには民事訴訟といった法的手続きを利用して解決をすることが考えられます。
しかし、可能な限り労使間での合意退職を目指すことが望ましいです。
会社側が退職金の上乗せや会社都合退職の提示を行い、従業員との合意を形成することで、紛争による会社側の負担も軽減され、本来の経営業務に力を注ぐことができます。
いかがでしょう。メンタルヘルス不調による休職者が増加する中、企業は適切な復職対応を行うことが求められています。
特に、復職の判断基準を明確にし、必要なプロセスを踏んで対応することで、労使トラブルを未然に防ぐことができます。
まずは就業規則の等の見直しからスタートし、休職・復職のプロセスの再構築を検討されることをお勧めします。
プロフィール
ひろたの杜 労務オフィス 代表(https://yoshismile.com/)
営業や購買、総務などの業務を会社員として経験したのち、社会保険労務士の資格を取る。いくつかの社会保険労務士事務所に勤務したのち独立開業する。現在は、労働者や事業主からの労働相談を受けつつ、社労士試験の受験生の支援をしている。