日常の労務手続き
- 人事労務・担当者全般、経営者向け
給与計算はじめ、社会保険手続きや年末調整等の労務に関する記事をまとめています。
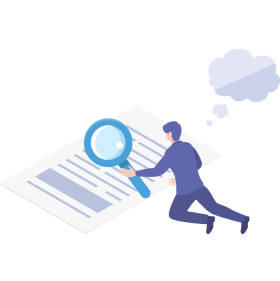
経営者や人事・労務、総務ご担当の皆様に知っていただきたい『知恵』と『知識』をお届けしている人事労務支援専門の会員制サイトです。
高年齢者等職業安定対策基本方針案について意見募集(パブコメ) 2026年2月4日
iDeCoライブ配信セミナーを開催 テーマは「知って得する制度改正と手続き… 2026年2月4日
令和9(2027)年暦要項を公表(国立天文台) 2026年2月4日
国民年金保険料の「2年前納」制度のページを更新 令和8年度の2年前納の情… 2026年2月3日
「個人情報保護委員会業務案内」を更新 2026年2月3日
【専門家コラム】2026年度税制改正大綱-法人税編他- 2026年2月3日
「インボイス制度特設サイト」をリニューアル(国税庁) 2026年2月2日
障害者雇用納付金の対象を常用労働者数100人以下の事業主にも拡大すること… 2026年2月2日
2月1日から3月18日までは「サイバーセキュリティ月間」 令和8年の実施につ… 2026年1月30日
給与計算はじめ、社会保険手続きや年末調整等の労務に関する記事をまとめています。
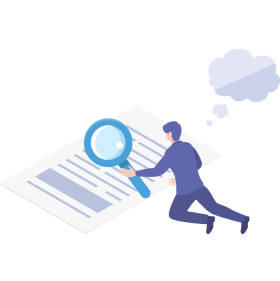
評価や賃金などの人事制度や退職金制度などに関する記事をまとめています。


オンライン 2026/02/18(水) /14:00~15:00
講師 : 株式会社HRbase
人事労務業務の生産性向上をテーマに、社労士の視点からAI活用の実践ポイントを解説するセミナーを開催します。株式会社HRbase 三田弘道氏を講師に迎え、AIの基礎や最新動向を整理しながら、人事労務業務で負担の大きい作業をどう効率化できるのかを具体的に紹介。さらに、情報漏えいや誤回答などAI活用時のリスクとセキュリティ対策についても実務目線で解説します。
【2025年対応】基礎から実務解説&演習で初心者でも即戦力になれる!「年末調整」実践セミナーDVDです。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応!
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き!
かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。
通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。
TEST
CLOSE