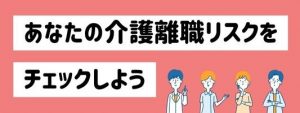2025年4月より全企業に義務化
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の
周知・意向確認、情報提供などの雇用環境整備
2025年4月から介護両立支援制度の強化等を企業に義務付けられました
少子高齢化の進行を背景に、介護を抱えながら働く方々が増えています。
2023年7月21日に総務省が公表した「令和4年就業構造基本調査」結果によると、過去1年間に家族の介護や看護を理由に離職した人は10万6,000人。
経済産業省は、家族等の介護をしながら働く人が2030年には約318万人、離職や労働生産性の低下などによる経済損失額は9.1兆円と推計しており、仕事と介護の両立支援に関する企業向けガイドラインの策定等や、介護にかかわる社会機運の醸成に取り組むと発表しました。
また、厚生労働省では、2023年11月、介護休業などの支援制度を知らないまま介護離職に至るケースが多いことを踏まえ、介護保険料の支払いが始まる40歳となった従業員全員に介護休業などの支援制度を周知することをすべての企業に義務づける方針を決定しました。この内容を盛り込んだ改正育児・介護休業法は、2024年5月24日に成立し、2025年4月から全企業に義務化されました。
義務化の背景にあるものとは?
介護は誰もが直面する可能性のある問題です。
しかし、いざ直面したとき、離職せず働き続けていくには、個人の力だけでは難しく、職場や上司の理解、会社の両立支援体制等が必要不可欠になります。
次のようなデータをご存じでしょうか。
- 働きながら介護を担っている人の約8割が40~60歳代
- 40~50代正社員の約4割が「今後5年間で親の介護の可能性がある」
- 介護をしながら、今の会社で仕事を「続けられないと思う」「続けられるかわからない」で77.4%
出典:厚生労働省「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」
ここからわかるのは、介護をする人の多くが、中堅社員、管理職等、職場の中心的役割を担う世代だということです。
また、8割近くの方が仕事と介護の両立について漠然と不安を感じているということです。
特に中小企業や労働集約型事業を行う企業、中堅層の厚い企業では、こういった貴重な人材を介護離職で失うことは、業績に大きく影響する可能性もあるため、できるだけ避けたいと考えていらっしゃるのではないでしょうか。
介護離職者を対象にした調査ではこのようなデータもあります。
- 介護離職経験者が介護を機に仕事を辞めた理由の第1位が「仕事と介護の両立が難しい職場だったため」59.4%
- 介護を始めてから、介護のための勤務先の制度の利用状況は「利用していない」が最も多い
- 勤務先制度を利用しなかった理由は「介護休業制度等の両立支援制度が整備されていなかったため」が最も多い
出典:厚生労働省「仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業(令和元年度)」
つまり、介護休業や介護休暇制度など法定の制度を単に導入しただけでは、介護離職は止めることができず、両立支援制度の内容が十分に周知されていること、実際に利用しやすい職場環境であるかどうかが重要なのです。
では、具体的に「介護があっても安心して働き続けられる職場」を実現するにはどうしたらよいのでしょうか。
本特集では、会社の必須対策となった「仕事と介護の両立支援」について、さまざまな角度から取り上げていきます。
2025年義務化対応と介護離職を防止する仕組みづくりに
介護従業員説明用セット~個別周知・意向確認、早期情報提供~
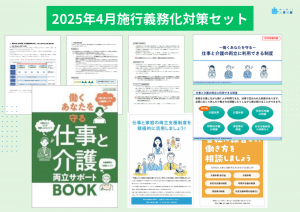 2025年4月から、改正育児介護休業法で義務化されている「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」 の実務対応に特化したセットです。
2025年4月から、改正育児介護休業法で義務化されている「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」 の実務対応に特化したセットです。
厚生労働省の通達や最新のQ&A等に基づき、人事担当者が押さえるべき事項をわかりやすく整理した実務ポイント集、従業員向け制度説明用動画、義務化対応ハンドブックなどを一式揃え、会社のスムーズな義務化対応を支援します。
本セットがあれば、 「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」のすべてが1つで完結!
さらに、ポスターひな型の活用で、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備が進められます。ぜひご活用ください。
人事担当者、管理職が押さえておきたい介護の重要ワード
要介護状態
育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態」(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない)のことをいい、介護保険制度の要介護認定を受けていなくても、介護休業は利用できます。
常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められており、座位保持、歩行、移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間などの乗り移りの動作)、水分・食事摂取、排せつ、意思の伝達など全12項目の状態から判断することになります。ただし、基準にとらわれて、介護休業の取得が制限されないように柔軟に運用することが望ましいとされています。
【トピックス】育児・介護休業法による介護休業等に係る「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」などを見直し(厚労省)(公開日:2025年2月14日)
対象家族
介護休業や介護両立支援制度等の利用ができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。対象家族の範囲は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子(養子含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。なお、介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子のみとなります。
地域包括支援センター
介護・福祉に関する、地域の「よろず相談所」。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといった専門知識を持った職員が、住民の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行っており、介護保険の申請窓口も担っています。各市町村が設置主体となり、中学校区(人口2~3万人)に1か所設置されています。
要介護認定(要支援認定)
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、日常生活の基本的な動作はほぼ自分で行うことができるが、家事や身支度等に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができます。 この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの判定を行うのが要介護認定(要支援認定)で、非該当、要支援1・2、要介護1~5までの区分があります。市区町村が実施しています。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護を必要としている人の状況や家族がどのようなことに困っているのかを把握し、必要な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるように、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。要介護者や要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして、介護支援専門員証の交付を受けています。
【社員向け】あなたの介護離職リスクチェック!
簡単チェック後は、内容をヒントに、家族と介護について話し合ったり、会社の支援制度や相談窓口を調べたり、介護スタート後の働き方をイメージしてみるなど、できるところから取り組んでいきましょう。
リスクチェックはこちら≫≫≫ https://www.kaiketsu-j.com/environment/7728/
【専門家コラム】仕事と介護の両立支援のポイント
介護に関する知識や、両立支援体制づくり等について、介護にかかわる各専門家によるコラムを順次掲載していきます。
【介護両立支援 × 人事労務】 企業が行う両立支援のあり方と実務の進め方
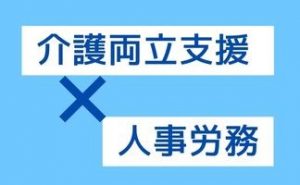 介護両立支援制度等の周知のポイントや、従業員の介護の問題を会社の課題としてどのようにとらえ、支援していくべきか、また、仕事と介護を両立する従業員が働き続けられるための体制づくりやその実務・進め方等、社会保険労務士による解説記事を掲載していきます。
介護両立支援制度等の周知のポイントや、従業員の介護の問題を会社の課題としてどのようにとらえ、支援していくべきか、また、仕事と介護を両立する従業員が働き続けられるための体制づくりやその実務・進め方等、社会保険労務士による解説記事を掲載していきます。
- 最新記事>>>【専門家コラム】介護休業取得促進のための雇用環境整備とは? 人事担当者が押さえておくべき実務のポイント
- 記事一覧はこちら>>>【介護両立支援 × 人事労務】企業が行う両立支援のあり方と実務の進め方
【連載】40歳以降の介護リスク増に備える 仕事と介護の両立のために知っておきたい大事な知識
 仕事と介護の両立支援の専門家、一般社団法人日本顧問介護士協会 代表理事 石間洋美氏による連載です。
仕事と介護の両立支援の専門家、一般社団法人日本顧問介護士協会 代表理事 石間洋美氏による連載です。
40歳を機に急激に高まる介護のリスクに備え、両立するための大事な知識について解説していただきます。
- 最新記事>>>第36回 介護施設を「選択する」タイミング
- 記事一覧はこちら>>>【連載】40歳以降の介護リスク増に備える 仕事と介護の両立のために知っておきたい大事な知識
2025法改正対応の実務お役立ちコンテンツ
オンデマンド配信【2025介護周知義務化対策】 仕事と介護 企業が行うべき両立支援と求められる両立支援
 働きながら介護をするビジネスケアラーが増加していることを背景に、2025年4月1日より全企業に、「介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置」が義務付けられることになりました。
働きながら介護をするビジネスケアラーが増加していることを背景に、2025年4月1日より全企業に、「介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置」が義務付けられることになりました。
施行開始までに、会社は、介護に直面した方への両立支援制度等の周知はもちろん、今は介護の必要はない方にも早い段階での情報提供、研修や相談窓口の設置等、介護と両立しやすい雇用環境の整備のため、さまざまな準備を進めていく必要があります。
本セミナーでは、2025年4月1日以降義務化される「仕事と介護の両立支援制度の強化」について法改正のポイントをわかりやすく解説するとともに、介護の現場や両立事例、仕事と介護を両立する上で企業に何が求められているのか等、生の情報をお伝えします。
レジュメ計117ページ分のPDF&受講者限定「仕事と介護の両立支援 法改正対応チェックリスト」付き
※2024年7月30日に開催したセミナーのZoom録画動画です。
介護個別周知&情報提供義務化対応ハンドブック『働くあなたを守る 仕事と介護 両立サポートBOOK』
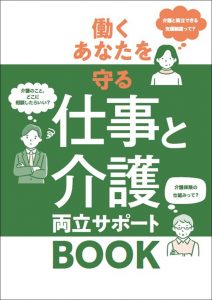 法律で求められることとなった介護に関する周知事項および情報提供事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本ハンドブックです。
法律で求められることとなった介護に関する周知事項および情報提供事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本ハンドブックです。
介護の備えから介護に直面した際の対応、地域の相談窓口である地域包括支援センターやケアマネジャー、介護保険制度やその利用方法などまで、また介護する人も介護される人も、今のキャリアや社会生活を大切にしながら、仕事と介護を両立していくための考え方や介護体制構築のポイントも随所に盛り込んでいます。
ぜひ、本ハンドブックを介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。
相談体制の整備に!介護相談窓口「顧問介護士」
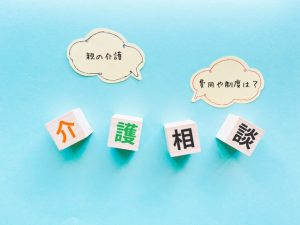 介護の相談窓口である「顧問介護士」を置いて介護離職を防ぎませんか?
介護の相談窓口である「顧問介護士」を置いて介護離職を防ぎませんか?
大切な社員が辞めずに働き続けてくれれば、新たにかかる採用コストを削減できます(※1人あたり平均約40万円かかる採用コストが削減)。
「顧問介護士」とは、介護関連の専門知識・資格を持った顧問介護士が介護にかかわる従業員の不安を解消し、「身近な人の介護があっても安心して働き続けられる」企業の環境づくりをサポートする福利厚生サービスです。
全国365日10時~19時、従業員からの介護および介護に派生する相談・お悩みに対応するLINE相談サービスが最大の特長。
合わせて、従業員向け介護セミナーの開催(年1回)、定期的な介護離職リスク診断の実施、会員専用の情報サイトによる情報提供等(広報誌、介護ガイドブック、動画コンテンツ他)が継続的に受けられます。
仕事と介護の両立支援に関するお役立ち情報サイト
育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
厚生労働省委託事業仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」