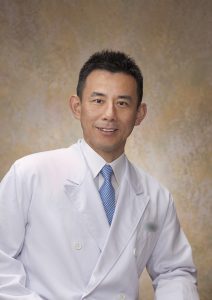
「介護離職」を防ぐために人事担当者が知っておきたいこと~在宅訪問医が見た介護のリアル
<合同会社DB-SeeD 代表社員 神田橋宏治>
現在、日本は人口の10%が80歳以上という超高齢化社会に入っています。そして80~84歳のうち4人に1人、85歳以上になると6割に「介護」が必要という時代になっています。
それに伴い、年間7万人の人が介護・看護を理由として離職しています。現在、介護離職を防ぐための様々な「仕事と介護の両立支援制度」が用意されています。
介護にはいろんな形があります。親孝行したいのは当然の気持ちですが、自分や自分の家族の生活も大切にしましょう。
介護は突然やってくる。その時忘れてはならない4つのポイント
まだ女性の多くが専業主婦だった時代。老親の介護は主にその家の主婦が担い、それを近くにいた兄弟姉妹が助けるという形が介護のあり方でした。
しかし現在、ほとんどの女性が働くようになりました。介護は制度として支える時代となり、2000年介護保険法が誕生しました。
介護は突然やってきます。例えば、久しぶりに帰省したところ、部屋が散らかり放題になっており、話もうまく通じなくなっている。ある日親が転倒、骨折して認知症も始まった、などです。
また介護は育児と違い、いつ終わるかわかりません。現在100歳以上人口は約10万人います。ですので、80歳の親が介護が必要になったとしたら、3年後に終わるかもしれないし、20年後!かもしれないのです。なので親が70歳代、80歳代に入る前に、あらかじめ最低限の介護に関する知識を持っておくことが大切です。
親の介護に直面した時、以下の4つを思い出しましょう。
① いきなり仕事を辞めない
会社や行政に様々な仕事と介護の両立支援のための仕組みがあります。会社の人事担当者に真っ先に相談しましょう。
② 親の住所地の地域包括支援センターに相談にいく
地域包括支援センターはワンストップで介護の体制等を整えてくれる公的機関です。「高齢者安心センター」といった名前になっていることもあります。親の住所地の自治体に聞けば、担当センターを教えてくれます。
③ 自分や家族の生活を一番に考える
育ててもらった親に恩返ししたいと思うのは自然なことです。しかし、先の見えない介護生活に疲れ果ててしまってはいい結果になりません。ケアマネージャーをはじめとした専門職にできる限り任せ、まずは自分や家族の生活を第一に考えてください。
④ 自分のところに親を呼び寄せるのは慎重に
自分のところに親を呼び寄せ同居することにはデメリットもあります。別の町に住んでいた場合、親にとってあなたの住んでいる町はまったく新しい土地です。見慣れた風景も、知っている商店も、昔からの友人もいません。その状況に適応するのには相当時間がかかります。当然あなたに対する依存は高くなります。それで親子ともども苦しんで、結局元の家にもどったり老人ホームに入ったりする例を、在宅訪問医として多く見てきました。
いろんな形の介護がある~在宅訪問医として見てきた事例から
子どもが親の介護をする、というのが当たり前だと思っていませんか。
実はいろんな形の介護があります。私は10年以上訪問医療に従事しています。対象は個人宅や老人ホームなどの施設です。そのなかで、印象深かった例をいくつかあげましょう(いずれも大幅に改変してあります)。
ケース1 超高齢男性の一人暮らし
木造で築50年以上の小さな家に住み、家はあちこち床もきしんでいます。その家で死んでいくつもりだと頑固として言い張ります。
すぐ近くに子どもたちが住んでおり交代で面倒を見ていました。彼は太平洋戦争前に上京、親方の下で修業して、独立・結婚。戦後すぐにこの家を建てました。ここには彼が仕事をして、妻と暮らし、子供を育て上げ、引退し、妻をこの家で看取った歴史が全部詰まっているのです。子供たちもそのことは十分理解していました。
最後まで入院することなくその家で最期を迎えました。ご家族も満足されていました。
ケース2 生活保護の男性患者
資産家の家に生まれましたが、家出同然で上京し、自分で事業を立ち上げます。妻と二人三脚で相当大きな事業になりましたが、その妻と離婚して二番目の妻と結婚。再婚した妻とも離婚し、その際財産のほとんどを持っていかれました。
ところで、私の診療中、何かあると電話一本で60代半ばの男性がかけつけます。最期を看取ったのもこの方だけでした。不良だったころ拾って雇ってくれたのがこの患者さんで、以来ずっと恩義を感じており、その方からの要望には常に応じてきたとのことでした。亡くなったあと、ポツポツと思い出話をする姿が寂しそうでした。
ケース3 有料老人ホームに入居する女性
7人兄弟の末娘で上は全部兄でした。彼女は自分の両親の世話に追われ、結婚することもなく、両親から相続した財産を使って老人ホームに入りました。
子どものいなかった彼女は甥姪を非常にかわいがっており、甥姪数名に囲まれてホームで亡くなりました。動かなくなった亡骸の前で泣き崩れていた甥姪の姿は今でも忘れられません。
その他にも、自然に二人で暮らしている同性愛者のカップル、1人暮らしで身寄りもないけれども近所付き合いが良く、いつも誰かしらが遊びに来て様子を見てくれていたアパートの住人など、今なお心から離れない在宅患者は枚挙に暇がありません。
--
現在、国は全力で介護問題/労働問題に取り組んでいます。高齢者の健康確保や若い頃からの健康管理を強化すると同時に、高齢者・外国人労働者を増やし介護離職者を減らすことにより労働力を確保しようという動きです。2025年4月からの改正育児介護休業法もその一環として施行されます。
会社が改正育児介護休業法について学び、従業員に周知することを通じて、従業員の介護離職や介護に伴う疲弊を防止しましょう。
プロフィール
このコラムをお読みの方におすすめの「介護両立支援」コンテンツ
- 【産業医・社労士執筆・監修】介護周知・情報提供用冊子『働くあなたを守る 仕事と介護 両立サポートBOOK』 >>>https://www.kaiketsu-j.com/product_detail/?id=1335
- 介護の義務化をまるごと支援!「2025年義務化対応 介護従業員説明用セット~個別周知・意向確認、早期情報提供~」>>>https://www.kaiketsu-j.com/training_tool_detail/?id=15001
- 仕事と介護の両立支援特集 >>>https://www.kaiketsu-j.com/feature/90/
- 仕事と介護両立支援実務支援コラム:【介護両立支援 × 人事労務】企業が行う両立支援のあり方と実務の進め方>>>https://www.kaiketsu-j.com/feature/11825/















