
【最新法改正対応】人事担当者必見!社会保険と給付金の基礎知識と実務ポイント
出産・育児・病気など、従業員のライフイベントに際しては、健康保険や雇用保険などの社会保険からさまざまな給付が受けられます。
しかし、これらの制度は複雑であり、さらに毎年のように法改正が行われるため、常に正確かつ最新の知識が不可欠です。
人事担当者には、日々の実務対応はもちろん、従業員から寄せられる質問や相談に対しても、迅速かつ的確に対応する力が求められます。
例えば、改正育児介護休業法で義務化された「育児両立支援制度等の個別周知・意向確認」では、社会保険や給付金など、お金に関する説明が避けられません。こうした場面で自信を持って説明するためにも、日頃から知識のアップデートが重要です。
そこで本シリーズでは、社会保険労務士試験の受験対策講座を主宰し、Youtubeチャンネルでも社会保険の知識についてわかりやすく発信されている社会保険労務士・竹本隆氏に、複雑な社会保険の制度や給付金の仕組みなどについて、最新の法改正情報も交えながら解説していただきます。
連載コラム
会社員を退職しても健康保険に加入できる 任意継続被保険者 NEW!
 会社を退職した後でも、一定の条件を満たせば、会社で加入していた健康保険に引き続き最大2年間加入を継続できる「任意継続被保険者」という制度があります。今回はこの制度について解説いたします。
会社を退職した後でも、一定の条件を満たせば、会社で加入していた健康保険に引き続き最大2年間加入を継続できる「任意継続被保険者」という制度があります。今回はこの制度について解説いたします。
ケガや病気のときにもらえる給付 傷病手当金
 病気やケガで、会社を長期間休まないといけないとなると仕事ができず、その間の収入がどうなるのか?という不安がありますよね。
病気やケガで、会社を長期間休まないといけないとなると仕事ができず、その間の収入がどうなるのか?という不安がありますよね。
そんなときに役に立つのが今回ご紹介する傷病手当金です。本コラムでは、その仕組みや注意事項について解説いたします。
出生時育児休業給付金
 子どもが生まれた直後は、育児はもちろんですが、それ以外にも役所への様々な手続きなどしなければならないことがあります。
子どもが生まれた直後は、育児はもちろんですが、それ以外にも役所への様々な手続きなどしなければならないことがあります。
そこで、産後8週間の期間に活用できる出生時育児休業、そして、その間に受け取れる給付金として今回ご紹介する出生時育児休業給付金があります。
本コラムでは、出生時育児休業給付金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。
育児休業給付金
 会社員が、育児のため仕事をお休みすると、その期間、一般には給与が支払われません。
会社員が、育児のため仕事をお休みすると、その期間、一般には給与が支払われません。
そこで、その期間の所得補償となるのが今回ご紹介する育児休業給付金です。本コラムでは、育児休業給付金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。
育児休業期間中の保険料免除
 日本の公的な医療保険制度や年金制度では、毎月保険料を納める仕組みになっていますが、会社員の方が育児休業を取得する場合は、その期間の保険料が免除になる仕組みがあります。
日本の公的な医療保険制度や年金制度では、毎月保険料を納める仕組みになっていますが、会社員の方が育児休業を取得する場合は、その期間の保険料が免除になる仕組みがあります。
本コラムでは、その保険料免除の仕組みや注意事項について解説いたします。
産前産後休業中の保険料免除
 日本の公的な医療保険制度や年金制度では、毎月保険料を納める仕組みになっていますが、会社員の女性が産前産後休業を取得する場合は、その期間の保険料が免除になる仕組みがあります。
日本の公的な医療保険制度や年金制度では、毎月保険料を納める仕組みになっていますが、会社員の女性が産前産後休業を取得する場合は、その期間の保険料が免除になる仕組みがあります。
本コラムでは、その保険料免除の仕組みや注意事項について解説いたします。
出産のときにもらえる給付 その2 出産手当金
 会社員の女性が、出産のためその前後で仕事をお休みすると、その期間、一般には給与が支払われません。
会社員の女性が、出産のためその前後で仕事をお休みすると、その期間、一般には給与が支払われません。
そこで、その期間の所得補償となるのが今回ご紹介する出産手当金です。本コラムでは、出産手当金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。
出産のときにもらえる給付 その1 出産育児一時金
 出産は病気やケガではありませんので、原則として、健康保険を使うことができず、出産にかかわる医療費は全額自己負担になります。
出産は病気やケガではありませんので、原則として、健康保険を使うことができず、出産にかかわる医療費は全額自己負担になります。
出産にかかる費用を軽減するために支給されるのが「出産育児一時金」です。本コラムでは、出産育児一時金の基本的な仕組みや申請の流れについて解説いたします。
執筆者プロフィール
 竹本 隆 社会保険労務士
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。
この記事をお読みの方にオススメの「社会保険とお金」関連コンテンツ
【オンデマンド配信】これだけはおさえておきたい!「今さら聞けない金融・経済のキホン」
 金融・経済の基礎知識がサクっと学べるなるほど!よくわかる!金融・経済の入門講座です。
金融・経済の基礎知識がサクっと学べるなるほど!よくわかる!金融・経済の入門講座です。
特に、新入社員研修等で金融商品や社会保障の制度を本格的に学ぶ前の下準備として最適な内容です。
これだけは知っておきたい社会保険の基礎知識BOOK
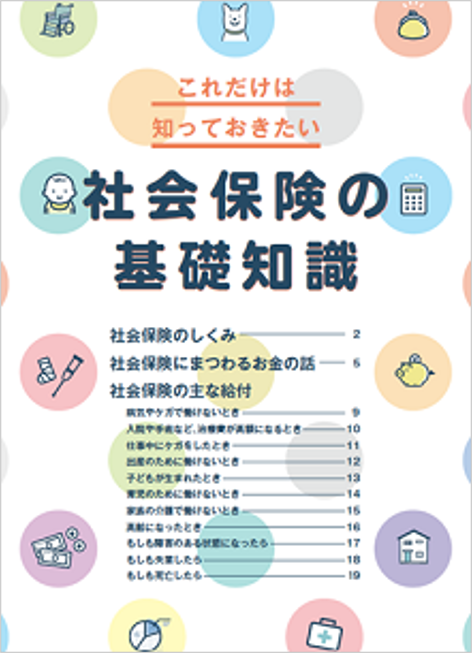 新入社員や社会保険適用拡大等で対象になった従業員への説明などに幅広くお使いいただける教育用冊子です。
新入社員や社会保険適用拡大等で対象になった従業員への説明などに幅広くお使いいただける教育用冊子です。
給与明細の見方から、社会保険の基本を社員に伝えることができます。また、いちばん気になる給付の話については、ケガ・病気をしたときの治療費やそれが原因で働けないとき、出産・育児・介護に関する給付など、知らないことで不利益を被ることがないよう、これだけは知ってほしいという知識だけを網羅的にまとめました。















